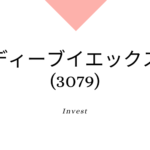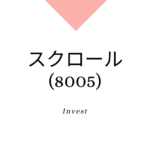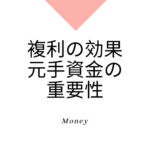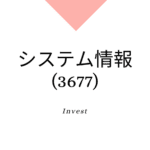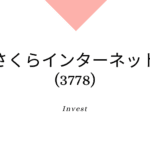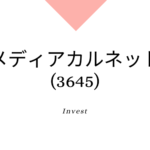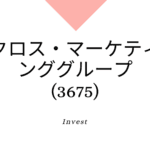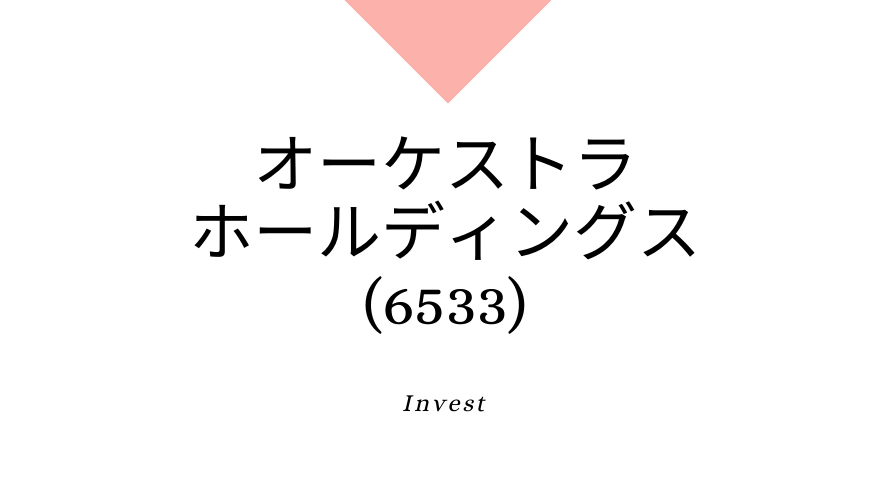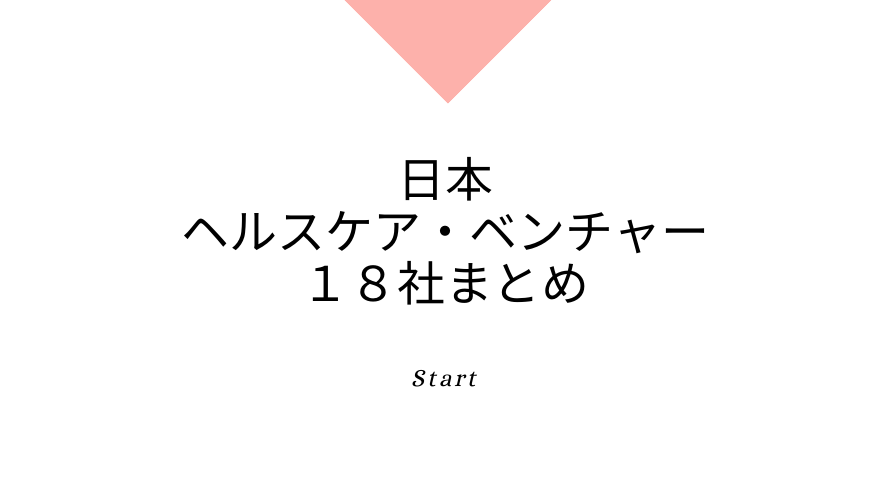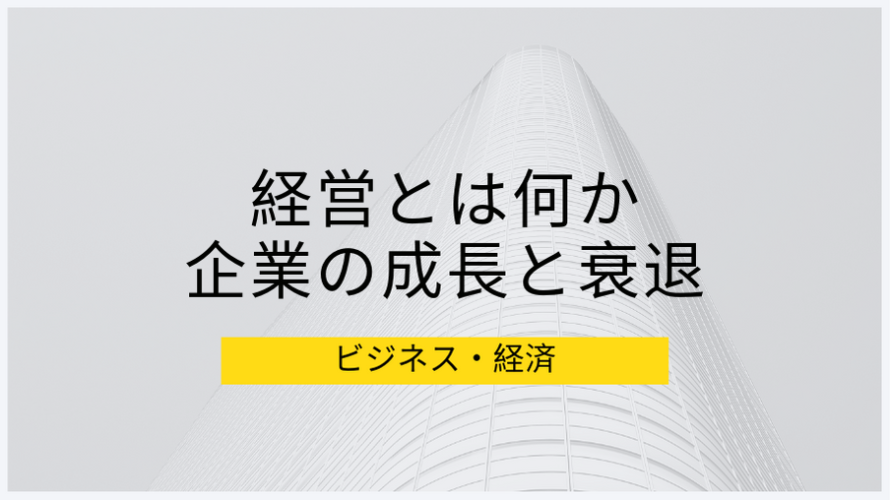ドーン(2303)、事業内容、ビジネスモデル、強みと成長可能性
- 2021.02.21
- 株式投資
-890x500.png)
ドーン(2303)の業績、売上高等を分析、考察しています。情報通信業界に属しており、時価総額が100億円前後ということで、ピックアップしています。
まずは、客観的に事業内容を精査する前に実績値としての数字を見ていきたいと思います。
株価関連情報
(調査日時:2021/1/7)
時価総額:112億円
PER(予):47.95倍
PBR:6.5倍
時価総額は、100億前後と高くありません。PER PBRの水準は客観的にみると非常に高いです。テーマ性が高いのか、利益水準が低いのかもしれません。
(調査日時:2023/5)
時価総額:66億円
PER(予):20.9倍
PBR:2.9倍
2021年の調査時点から株価は40%ほど下落しています。バリュエーション的にはやはり高かったですね。
株価チャート(10年)
2016年に大きく高騰しているのと、2021年にも高騰しています。タイミングによっては高騰することがある銘柄という感じです。長期的に見れば、右肩上がりという感じは間違いなさそうです。
株価チャート(5年)
5年というスパンで株価を見ると、横ばいという感じです。
株価チャート(1年)
直近は、2021年に高値をつけてから下落傾向にあります。
売上高推移
(単位:百万円)
2016年:753
2017年:788
2018年:836
2019年:893
2020年:1,050
売上高は順調に増えています。16年〜19年の成長率はそこまで高くはないのですが、2020年に過去と比べると大きく成長しています。何かしら動きがあるかも知れません。
営業利益推移
(単位:百万円)
2016年:108
2017年:125
2018年:162
2019年:200
2020年:290
営業利益の水準はそごで高くありません。営業利益率は、29%なので、非常に高い水準と言えるでしょう。ビジネスモデル的に、何かしら他社が参入していないものを提供しているかも知れません。
当期利益推移
(単位:百万円)
2016年:101
2017年:89
2018年:114
2019年:156
2020年:200
当期利益も同様で、規模的には小さいですが、少しずつ成長している様子が理解できます。
ROE推移
(単位:%)
2016年:8.7
2017年:7.2
2018年:8.5
2019年:10.5
2020年:12.1
ROEは、近年改善傾向にあります。10%台なので悪くはないでしょう。
有利子負債推移
(単位:百万円)
2016年:-
2017年:-
2018年:-
2019年:-
2020年:-
有利子負債はありません。
現金等推移
(単位:百万円)
2016年:188
2017年:280
2018年:333
2019年:378
2020年:528
現金は順調に増えています。2016年、直近までは現金があまりなかったのですが、20年には5億円近く保有しています。
キャッシュフロー推移
営業活動のキャッシュフロー
(単位:百万円)
2016年:169
2017年:41
2018年:181
2019年:114
2020年:293
営業キャッシュフローも、利益水準とほぼ大差はありません。変動もそこまで無さそうです。2017年に一時的に減っている点は少し気になる部分です。
投資活動のキャッシュフロー
(単位:百万円)
2016年:-168
2017年:62
2018年:-112
2019年:-49
2020年:-119
投資の水準も高くありません。多くても1億円半ばなので、規模の大きい投資も必要がないのでしょう。
財務活動のキャッシュフロー
(単位:百万円)
2016年:-4
2017年:-11
2018年:-15
2019年:-19
2020年:-23
特に大きな動きはありません。
フリーキャッシュフロー
(単位:百万円)
2016年:-
2017年:103
2018年:68
2019年:64
2020年:173
フリーキャッシュフローはポジティブに推移しています。額としてはそこまで大きくはありません。
事業内容
ドーン株式会社は地理情報システム(GISシステム)のソフトウェア開発を行っている企業です。このシステムは主に地方の公共団体や民間企業のエネルギー関連施設や都市設備などに使用されています。
製品事業は大きく分けて、GISシステムとクラウドサービスの2つです。では、これら2つのサービスをそれぞれ見ていきましょう。
GISシステム
GeoBase.NETと言われるGISシステムが主力製品です。
そもそもGISシステムとは、空間を対象としたデータの構築・解析を行えるようにしたシステムです。地球上の地理情報をコンピューターにより可視化し、情報を導き出してくれます。例えば、「現在地から1番近いコンビニの場所は?」などの問い、GISシステムは答えてくれます。
GeoBaseとは、そのGISシステムをより高速に動かし、システム上の情報の表現方法を大きく広げる事を可能にしたものです。
さらに、GeoBase.NETは加えて次のような特徴があります。
・さらに優れた表現方法の実現
⇒より直感的に伝わりやすい表現が追加
・豊富な機能
⇒表示方法の選択と構築がより簡単に可能
・超高速地図表示
⇒欲しい情報をよりスムーズな操作で表示が可能
・大規模運用
⇒数万台からの操作でも高速表示が可能
・クラウド対応
⇒自社でサーバーを持ち運用する必要がないため、初期コストが安価。また、クラウド環境でも変わらぬ性能。
GeoBase.NETは警察、消防といった自治体から農業や民間企業まで幅広い分野で採用されています。
クラウドサービス
地域の安全・安心をサポートするクラウドシステムの開発を行っています。その製品はさまざまで、あらゆる観点から地域の安全・安心をサポートするシステムを提供しています。それでは製品の詳細について見ていきましょう。
NET119緊急通報システム
NET119緊急通報システムは聴覚障害、言語障害を持った方でもスマートフォン、携帯電話1つで簡単に119番通報ができるシステムです。
特徴として、
・外出先からでも緊急連絡が可能
・事前登録制で「自宅住所」や「よく行く場所」を登録できる
・家族情報や自身の持病の登録も可能
などが挙げられます。
Live110映像通報システム
Live110映像通報システムは110通報した人がスマホ等で撮影した映像を警察官がリアルタイムで見られるといったサービスです。現場の情報を視覚的に伝えることが可能です。
Live119映像通報システム
Live119映像通報システムは119通報した人がスマホ等で撮影した映像を消防官がリアルタイムで見られるといったサービスです。現場の情報を視覚的に伝えることが可能です。
AED GO ‐AED運搬支援システム‐
AED GOは心肺停止等の発生した現場にAEDをより迅速に届けられるようなシステムです。119番通報と連携し、近くの人が現場までAEDを届けることを目的としたシステムです。
DMaCS 災害情報共有サービス
DMaCS 災害情報共有サービスは災害時、被害者が情報を報告し、まとめることで被害状況や災害規模を迅速に共有できるサービスです。
すぐメール
すぐメールは身の回りに起きた緊急事態をより早く周りに伝えることのできるサービスです。地図サービスとも連携し、文字媒体だけの情報でなく、視覚的にも情報を共有することが可能です。
まちかど案内まちづくり地図
まちかど案内まちづくり地図は地方自治体や地域のための情報集約地図サービスです。バリアフリー施設に関する情報を地図上でまとめるなど、その地域限定でより詳細な地図情報の共有が可能です。
まちかど地図Pro
まちかど地図Proはサーバーを持つ必要のない、低コストで構築可能な地図サービスです。インターネット環境のみで導入可能なため手軽にGISを使用できます。
その他にもGISをベースとした利便性の高いサービスを提供しています。その他サービスの情報はこちらに詳細があります。
今後と考察
(2021年2月調査時点)
地理情報システムを販売する当社、ビジネスモデルとしては、地理情報システムのエンジンをSI事業者を通してエンドユーザーに販売する形態を多くとっている模様です。
自社で、エンドユーザー向けのシステムを開発販売しているというよりは、販売するアプリケーションサービスに組み込まれるソフトウェアを販売しているというイメージに近いでしょう。
顧客としては、警察等の官公庁や通信、電力などのインフラ事業者がメインとなっている模様で、これまではSI事業者を通して販売していた形態がメインでしたが、クラウドサービスを通じて、直接エンドユーザーにサービスを提供するモデルも開始しています。
NET119緊急通報システム等が、クラウドサービス事業の一例となります。
クラウド利用料も、直近では順調に伸びており、ライセンス販売の単発での売上は減少傾向にある点も良いポイントだと言えるでしょう。
防災や防犯がテーマの銘柄なので、テーマ性はありつつも、自治体や官公庁に依存するビジネスモデルであるため、予算の確保や受注までのプロセスなどは一般の民間企業とは異なる点に注意が必要です。
テンバガー可能性
(2021年2月調査時点)
「C」
※「S」、「A」、「B」、「C」、「D」の5段階で勝手に評価した場合です。
参考記事:【まとめ】小型、成長株のおすすめスクリーニング方法、実践編
参考記事:小型成長株、銘柄一覧【注目の新興銘柄40社を独自調査】
※本記事に掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものです。特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また記載事項個人の調査に基づくものであり、100%正確であるとは限りませんので。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
最後に個別株投資の基礎を学ぶことは、将来の資産形成や財務の知識を高めるために非常に重要です。以下では、お金をかけずに効率的に学ぶことができる3つの簡単な方法をご紹介いたします。
方法①:無料の勉強会・セミナーに参加して体系的に基本を学ぶ
独学で学ぶ際に、無料セミナーに参加することは手軽でおすすめです。
セミナーでは、必要なポイントに絞って学ぶことができ、かつ、一般的な投資参加者の視点を得ることができます。
【無料開催中の勉強会・セミナーの一覧】
◎株式投資の学校
受講生の7割以上がプラスの運用成績を出している、ファイナンシャルアカデミーの人気スクールです。
体験セミナーでは、①お宝銘柄が見つかる3つの基本、②売買タイミングを判断する重要視点、③安定的に利益を出すためのリスク管理法、の3つの視点を学ぶことができます。
8割が損をすると言われる株式投資で、運用実績がマイナスのスクール受講生は、わずか9.4%とHP上では明言しているので、コンテンツにはかなり自信があるのでしょう。
>>【公式】https://www.f-academy.jp/
◎お金の学習・相談サービス『マネイロ』
資産運用やお金の増やし方をプロから動画視聴形式で学べるサービスです。カメラオフ+発言なしで気軽に参加できます。
つみたてNISA、iDeCo、投資信託などの資産運用について、初心者の方にもわかりやすいコンテンツです。
オンラインセミナーは1回30分、スマホでの視聴もOKなので、自宅やカフェからも気軽に参加できるのは嬉しいポイントです。
>>【公式】https://moneiro.jp/
◎投資の達人になる投資講座
投資初心者から経験者まで累計25万人以上が受講したオンライン投資セミナーです。
特徴としては、①講師が営業マンではなく投資の実践者なので、投資のリアルな話が聞ける点、②世界三大投資家ウォーレン・バフェット氏の元義娘、株式投資分析の世界的権威ジェレミー・シーゲル教授など著名な方々から直接情報を得ている点、③他で聞けない投資のノウハウが得られる点、です。
2021年には、最も信頼されるオンライン投資セミナーにも選ばれています。
>>【公式】https://toushi-up.com/
方法②:SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用する
SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用して銘柄を見る習慣をつけることも効果的です。
スクリーニング機能を使うと、さまざまな指標を組み合わせて効率的に銘柄を見つけることができます。
SBI証券では3,600以上の銘柄が取り扱われていますが、スクリーニングを上手に活用することで、素晴らしい銘柄に出会うことができます。
関連記事:小型株・成長株、銘柄一覧まとめ【日本の有望銘柄80社をブログで紹介】
方法③:著名な投資家の本を読む
以下の関連記事で、個人的に読むべき10冊をまとめています。
著名な投資家の本を読むことは、投資における知識と洞察を深めるために重要です。これらの本は、成功した投資家の経験と教訓に基づいて書かれており、貴重な情報を提供してくれます。
投資家の視点や戦略を学ぶことで、市場の動向やリスクの評価についての理解が深まります。
また、投資家の成功や失敗のエピソードを通じて、心構えやリスク管理の重要性も学ぶことができます。これらの本は投資初心者から上級者まで役立つ情報を提供し、自身の投資戦略を構築する上で不可欠な道しるべとなります。