農業総合研究所 (3541)業績分析、事業内容、強みと成長可能性
- 2019.03.22
- 株式投資
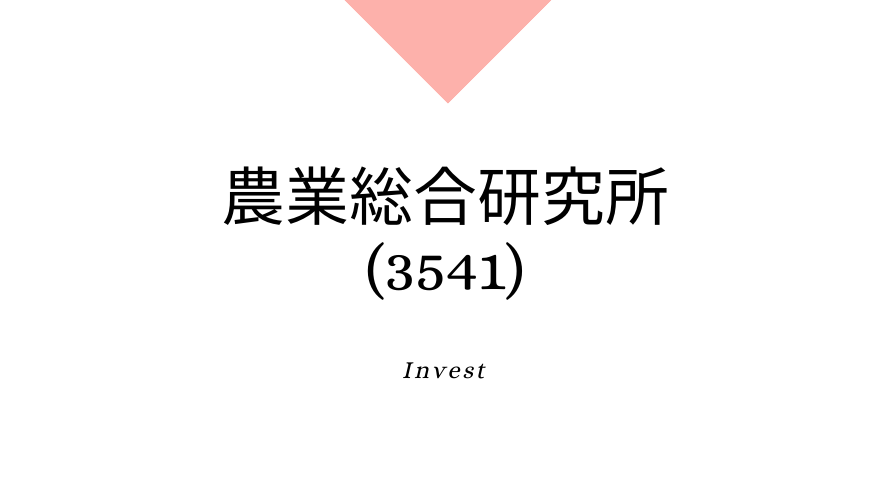
農業総合研究所、事業内容
農家の直売所事業を展開。
農家とスーパー等をつなぐことをメインの事業としています。事業の形態としては卸です。
プレイヤーとしては、1.生産者(農家) 2. 当社 3. スーパー等の小売の3者に大きく大別されます。
それぞれの販売契約は3種類あります。ここがビジネスモデルを理解する上では重要となってきそうです。
委託販売システム
スーパーと当社は在庫リスクを持たず、生産者が在庫リスクを持つモデル。
生産者は、販売先と販売価格を自分自身で決定することができ、農産物市場を介するよりも多くの収益を得ることができます。
スーパーと当社は販売代金から手数料をもらう仕組みです。
その他農業総合研究所は、集荷場から販売店舗までの物流費に見合う手数料などを徴収しています。
このモデルだと農業総合研究所は物流関連の価値を提供していることが理解できます。
集荷場での集荷、商品へのバーコード発券と貼り付け、各店舗への発送などの価値を提供しています。
また、生産者は当社の集荷場を利用する際に登録料を支払い、年会費を支払うことになります。
この点もストックの収益となります。
買取委託販売
委託販売システムと異なり、農業総合研究所が在庫リスクを負うモデルです。
売上高 – 販売店手数料 – 仕入れ高 = 農業総合研究所の取り分
ということです。
卸販売
農業総合研究所が生産者から買い取り、スーパーへ販売するモデル。
スーパーが在庫リスクを持ち、価格決定権を持ちます。
そのため市場からの買取価格と同等かそれ以下になる特徴があります。
以上、3つの形態があることがわかりますが、それぞれ誰が在庫リスクを持つのか、誰が価格決定権があるのか、という点で利益率も異なることが理解できます。
H30年8月末時点の重要な数字は以下の通り、
集荷場数 86 (直営24/提携62)
スーパー等店舗 1,197
登録生産者数(人)7,845
数字で見る農業総合研究所
決算年月 2018年度8月(単位 百万円)
売上高 2,310
当期利益 △29
営業CF △53
投資CF △77
財務CF △60
現金、現金同等物 808
有利子負債 148
ROE – %
従業員数 105名
農業総合研究所、注目点
・登録生産者、スーパ等店舗は順調に増えている点
・農家の直売所事業の流通総額も増えている点
・集荷場で集めた生産者の農作物に、各スーパー用のバーコードを発券できるシステムを保有
・各販売所での販売状況をデータで収集、ポータルサイト上で生産者に提供している点(当社にもデータが集まる)
・農家の加工業務を一括して請け負う加工センターの開発は農家の課題解決に資する、農家は生産に集中できる点。
・日本郵便との協業の取り組み。
参考:日本郵便株式会社九州支社との鳥栖センター開設に関するお知らせ
・生産者とのネットワークならびに集荷場という物流拠点を生かして、農業資材の販売を開始「農直 – のうちょく-」、クロスセルでトップラインを伸ばせる可能性
参考:登録生産者向け「農業資材販売サイト」スタートのお知らせ
農業総合研究所、懸念点
・イオンリテール、阪急オアシスへの販売依存度が高いこと。(H30年8月期、それぞれ13%, 11.7%)
・農作物相場は価格変動する市場であり、それに応じて当社の業績が変動する可能性がある点。
・スーパーとしては仕入れコストを抑えられるから、卸販売を進めたい可能性あり。スーパーの業績が悪化したり、小売の力が強い場合、不利な契約に切り替えられる可能性あり。
・H30年8月期、委託販売システムの売り上げの伸びよりも買取委託販売の伸びの方が高いこと。
経営者はどんな人か。
代表取締役社長は、及川 智正 氏という方です。以下略歴となります。
平成9年4月 株式会社巴商会入社 平成18年4月 エフ・アグリシステム株式 会社入社 平成19年10月 当社設立 代表取締役就任(現任)
出典:当社HPより
インタビュー記事がありました。
参考記事:Vol.36 株式会社農業総合研究所 代表取締役社長 及川 智正氏
父親の影響と大学時代の部活動の影響が大きいようです。農家として苦労している父親や祖父の話考えるきっかけとなっていたという点は、面白いですね。
すでに若い頃から農業に対する課題意識を持たれていたことが分かります。
特に面白い発想として、合同説明会での会社の選び方、
「もし会社を辞めたとしたら、ここの中で入りたい企業はどこか」という内容のアンケートを取り、その中で最も得票数が多かったのがガス専門商社の巴商会でした。全国各地に営業所がありましたが、働くならば一番厳しいところに行きたいと言ったところ、宇都宮行きを命じられました。
出典:Vol.36 株式会社農業総合研究所 代表取締役社長 及川 智正氏
これは今の就活生の参考にもなるかもしれません、自社以外でこの会社に行きたいと思える会社をアンケートで聞くっていうのは普通の人はなかなか発想できないし、そして実行に移せないと思います。
こういうストーリーはやはり起業家っぽいです。
農業の仕組みを変えないといけないと壮大な目標を持っていながら、現場で働く重要性を認識している点は、やはり農家としての家庭にいたからこその発想だと思います。
いくら理想を掲げても、現場を分かっていないと何も解決しないし、人も巻き込めないですからね。
関連記事:現場力とは何か – 現場力を鍛え、高めるために経営者ができること
この現場で自分で発見したことがやはり重要だと気付かされる内容です。
・農家として、感謝される機会の少なさ
・農家として情報発信することの難しさ
企業の最初の事業アイデアの農業コンサルティングが大失敗に終わった話なども創業期の試行錯誤がリアルに伝わってきます。
作物をもらい駅前でゴザを敷いて売って現金化するという作業を繰り返すうちに、農家の間で「東京から来たお兄ちゃんに野菜や果物を与えると高く売ってきてくれるらしいよ」と噂になり、多くの農家から作物が届くようになりました。僕は作物ではなく、お金が欲しかったのですが・・・。
もし、農業総合研究所の創業ストーリーを詳しく知りたい、人となりを少しでも理解したいということであれば、このインタビュー記事はとても参考になります。株主としては、こういう背景も知った上で企業を長期で応援したいですよね。
これから起業を考える人も一読の価値はあります。
株価水準
2019年3月時点
時価総額:約172億円
PER(会社予想)約287倍
農業総合研究所、まとめ
経営者の強い思いがあって、今日の農業総合研究所があるのだということがインタビュー記事を通して理解することができました。
ただ、理想の実現には時間かなり時間を要するのではないかという印象もあります。
理由としては、
・日本の小売の力が強い点、交渉力は小売がやはり強い
・日本の消費者は安いものを求める傾向
・実質賃金は低下傾向にある、消費増税に伴ってさらに財布の紐が硬くなる可能性
今後の外部環境の影響は受けてしまう可能性はありますが、農業のプラットフォーム事業としては面白い取り組みだと思い注目に値します。
農業の仕組みそのものを変えて、農業をより持続的なものにするというビジョンは現在の日本の農業が直面する課題を解決につながる壮大なビジョンです。
ビジネスの実態や数字を見てみても、堅調に成長している模様です。当社の強みとしては、強い課題意識、ビジョンから色んなプレイヤーを巻き込むことができる力にあると思っています。
先日プレスリリースした日本郵便との取り組みなどが好例です。
日本の農業をどうにかしないといけない、という課題意識を持った人たちは数多くいるはずで、その人たちを巻き込むことができれば、大きな動きを作り出すことができるのでしょう。
最後に個別株投資の基礎を学ぶことは、将来の資産形成や財務の知識を高めるために非常に重要です。以下では、お金をかけずに効率的に学ぶことができる3つの簡単な方法をご紹介いたします。
方法①:無料の勉強会・セミナーに参加して体系的に基本を学ぶ
独学で学ぶ際に、無料セミナーに参加することは手軽でおすすめです。
セミナーでは、必要なポイントに絞って学ぶことができ、かつ、一般的な投資参加者の視点を得ることができます。
【無料開催中の勉強会・セミナーの一覧】
◎株式投資の学校
受講生の7割以上がプラスの運用成績を出している、ファイナンシャルアカデミーの人気スクールです。
体験セミナーでは、①お宝銘柄が見つかる3つの基本、②売買タイミングを判断する重要視点、③安定的に利益を出すためのリスク管理法、の3つの視点を学ぶことができます。
8割が損をすると言われる株式投資で、運用実績がマイナスのスクール受講生は、わずか9.4%とHP上では明言しているので、コンテンツにはかなり自信があるのでしょう。
>>【公式】https://www.f-academy.jp/
◎お金の学習・相談サービス『マネイロ』
資産運用やお金の増やし方をプロから動画視聴形式で学べるサービスです。カメラオフ+発言なしで気軽に参加できます。
つみたてNISA、iDeCo、投資信託などの資産運用について、初心者の方にもわかりやすいコンテンツです。
オンラインセミナーは1回30分、スマホでの視聴もOKなので、自宅やカフェからも気軽に参加できるのは嬉しいポイントです。
>>【公式】https://moneiro.jp/
◎投資の達人になる投資講座
投資初心者から経験者まで累計25万人以上が受講したオンライン投資セミナーです。
特徴としては、①講師が営業マンではなく投資の実践者なので、投資のリアルな話が聞ける点、②世界三大投資家ウォーレン・バフェット氏の元義娘、株式投資分析の世界的権威ジェレミー・シーゲル教授など著名な方々から直接情報を得ている点、③他で聞けない投資のノウハウが得られる点、です。
2021年には、最も信頼されるオンライン投資セミナーにも選ばれています。
>>【公式】https://toushi-up.com/
方法②:SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用する
SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用して銘柄を見る習慣をつけることも効果的です。
スクリーニング機能を使うと、さまざまな指標を組み合わせて効率的に銘柄を見つけることができます。
SBI証券では3,600以上の銘柄が取り扱われていますが、スクリーニングを上手に活用することで、素晴らしい銘柄に出会うことができます。
関連記事:小型株・成長株、銘柄一覧まとめ【日本の有望銘柄80社をブログで紹介】
方法③:著名な投資家の本を読む
以下の関連記事で、個人的に読むべき10冊をまとめています。
著名な投資家の本を読むことは、投資における知識と洞察を深めるために重要です。これらの本は、成功した投資家の経験と教訓に基づいて書かれており、貴重な情報を提供してくれます。
投資家の視点や戦略を学ぶことで、市場の動向やリスクの評価についての理解が深まります。
また、投資家の成功や失敗のエピソードを通じて、心構えやリスク管理の重要性も学ぶことができます。これらの本は投資初心者から上級者まで役立つ情報を提供し、自身の投資戦略を構築する上で不可欠な道しるべとなります。

-2-150x150.png)
-150x150.png)
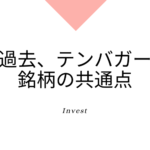


のコピー-150x150.png)

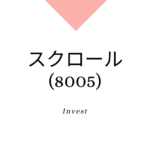




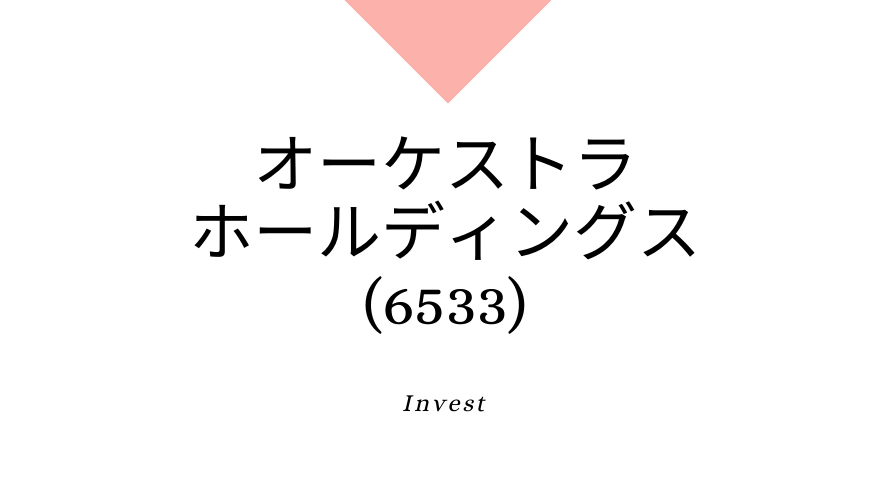
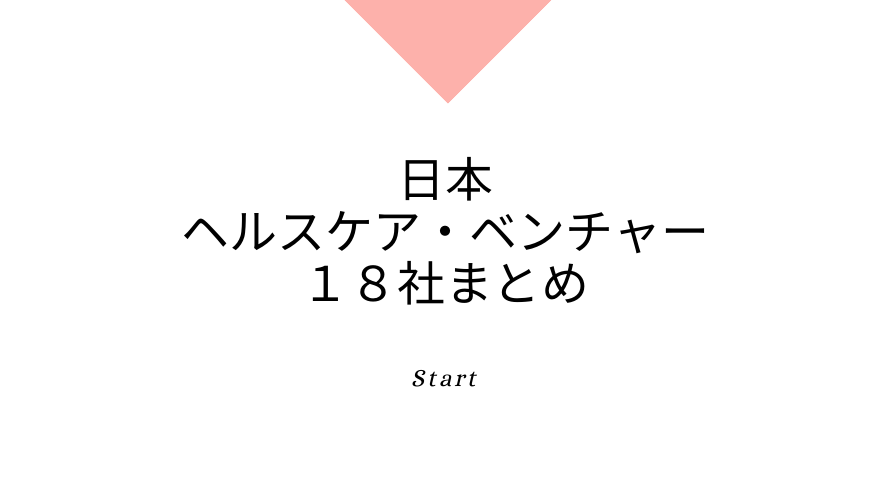
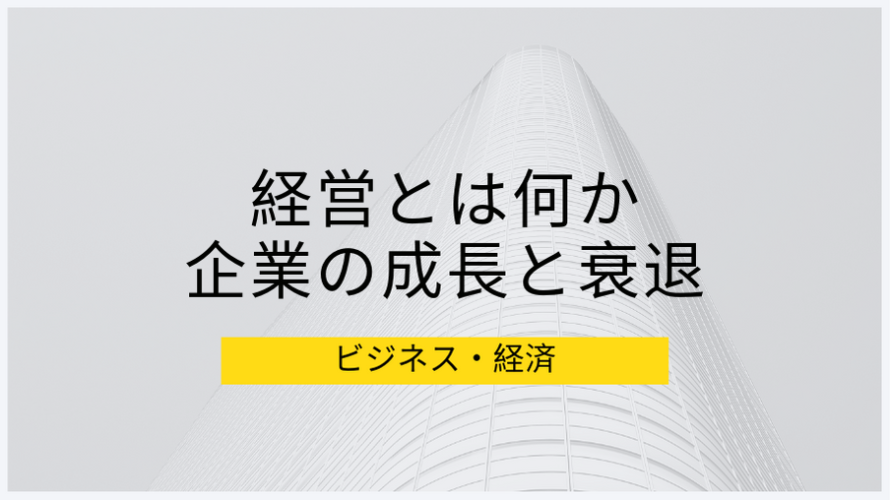


コメントを書く