すららネット(3998)業績、株価分析、強みと成長可能性
- 2019.03.24
- 株式投資
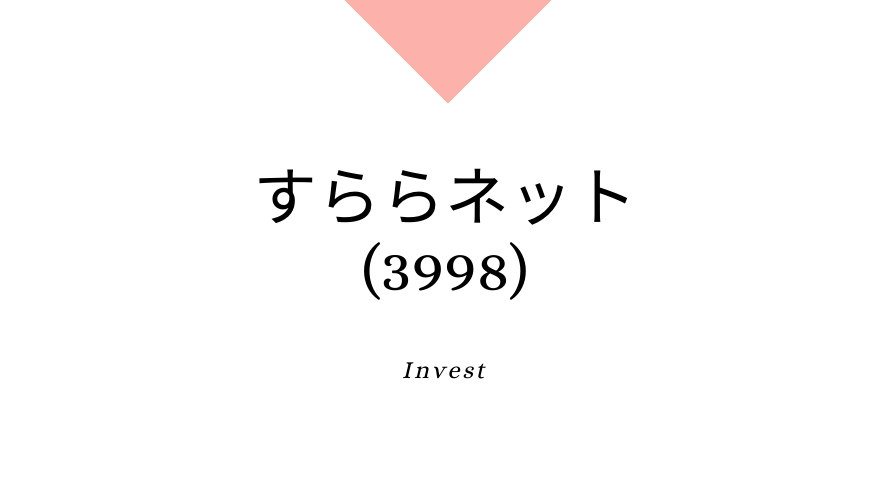
すららネットの事業内容
・オンライン学習教材「すらら」を提供。
紹介ページを見ていただければ、他の教材との違う点を理解できます。
デジタル教材は、動画配信型、問題集型、ゲーム型の3つのプロダクトが多いが、それぞれがバラバラである点に問題があります。
当社は、その三つの要素をそれぞれ上手く組み合わせた点が他社製品と違う点であると強調しています。
特にアダプティブラーニング機能は注目、生徒の解答情報から苦手分野を特定して、生徒に合わせた問題を提示することが可能となっています。
アダプティブラーニングとは、
学習者1人ひとりに最適な学習内容を提供することで、より効率的、効果的な学習を実現する方法。従来も、生徒の習熟度に応じて指導方法を変えることは行われていたが、あくまでも教員の経験に基づく感覚的なものであった。近年は、生徒の学習状況を蓄積するとともに、AIなどICT技術によってより客観的に分析し、生徒の習熟状況や不得意分野を明らかにすることで、それぞれの生徒にもっとも適した教材の提案が行われている。アダプティブ・ラーニングによって、生徒それぞれにより細やかな学習指導が可能になるほか、生徒間で学習の進捗状況や習熟度が大きい場合の指導に役立つ。
また、「すらら」は他社とのコラボレーションも実施しており、他社コンテンツをすらら上で提供するプラットフォーム戦略を取っています。
この点、e-learningのデファクトとなれば、拡張性のあるビジネスとなりそうです。
すららの法人顧客は、反転授業で利用されているという記載があり、反転授業とは何か調べてみました。
ブレンド型学習の形態のひとつで、生徒たちは新たな学習内容を、通常は自宅でビデオ授業を視聴して予習し、教室では講義は行わず、逆に従来であれば宿題とされていた課題について、教師が個々の生徒に合わせた指導を与えたり、生徒が他の生徒と協働しながら取り組む形態の授業である。
出典:Wikipedia
面白いですね、従来型の授業だと一斉に同じ内容を多数の生徒に教えるで、理解度の差が原因でついてこれない生徒が発生します。
また理解できる生徒は、平均レベルまで引き下ろされることになります。
これを解消するのが、反転授業でしょう。生徒の自主性が大前提として必要で、すららなどのデジタル教材が不可欠です。
この仕組みが導入されれば、先生が個々の生徒に時間を割くことができます。
従来型の教育の弊害である、学習の遅れや画一的な教え方を解決する手段としても注目に値します。
すららを導入した学習塾などの法人に対して、経営支援のサービスも提供しています。
プロダクトと合わせて、経営支援まで行うというビジネスモデルは、ヘアサロン向けにプロダクトを提供しつつ、サロンの経営支援を行う「コタ」(4923)のモデルに似ていると思います。
課金の基本モデルは、月額のサービス利用料と、生徒ID1つにつき課金される月額利用料です。
学習塾と学校では多少課金のモデルが異なり、学校法人は一定の数までは固定額の利用料金で対応している模様です。
大手の学習塾に採用になることや、学校公認の学習教材となれば一気に生徒数を獲得ができ、事業が拡大されることが理解できます。
数字で見るすららネット
有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)より
決算年月 2017年12月(単位 百万円)
売上高 731
当期利益 108
・マーケット別販売実績
学習塾 463 (前年同期比 120%)
学校 231 (前年同期比 132%)
BtoC 31 (前年同期比 156%)
その他 4 (前年同期比 106%)
営業CF 166
投資CF △113
財務CF 243
現金、現金同等物 436
有利子負債 –
ROE14.8 %
従業員数 27名
・その他、重要なKPI
H29年、12月末時点
すらら導入校数 717
すらら利用ID 50,978
すららネットの注目点
・e-learning市場は拡大傾向であること
・導入校数の数は一定で伸びていて、すららID数の伸びが著しい点。(H28年 37,954 > H29年 50,978)
・自社で塾を展開していない中立な立場であること、会社に色がない(プラットフォームとしては重要な要素)
・プロダクトの評判を見ると、学習に遅れがある子供には評判が良さそう。ターゲティングがしっかりできている印象
参考ページ:数学テスト最低ランク中2が「すららネット」教材を1か月使ってみた結果!
・低価格で広範囲な学年に対応
・対応する教科書の幅が広い、ほぼ全てに準拠している点
参考:中学生の通信教育「デキタス」「すらら」を7つのポイントで比較!
すららネット懸念点
・大手企業の競合各社の存在(スタディサプリ、学研ゼミ、スマイルゼミ、進研ゼミ、デキタスなど)
・学校法人の場合、1件の契約解除のインパクトが大きい可能性がある
経営者はどんな人か。
代表取締役は、湯野川 孝彦 氏という方です。以下略歴となります。
大阪大学基礎工学部卒。
東証一部上場企業の新規事業担当役員時代にeラーニング教材すららの事業を企画・開発。2010年、すらら事業を MBOにより買い取り独立した。すららはそのアダプティブな機能により、生徒一人一人の学力に応じて楽しみながら学べる教材として急速に広まっており、「多様化への対応」がテーマであった2016年の教育再生実行会議においては有識者として参画した。
出典:当社HPより
インタビュー記事がありました、この記事はIRだけでは理解できないような深い戦略や優位性を理解することができるので、必読だと思います。
参考になったポイントとしては以下、
・ベンチャー・リンク時代に学習塾のFC経営を経験、そこから子供の成績が伸びないという課題を身を以て実感。
・個別指導のあり方に課題を感じていたこと。
この点は、共感します。働いている人たちが大学生のアルバイトだったりするので、教え方の質にバラツキがあること。
そして教えている先生自体が高学歴であったりするので、学習が遅れている子供たちがどこでつまずくのかということを理解できないこともあるかと思います。
・進学塾のマーケットはレッドオーシャンだが、すららがターゲットにしている学習の遅れの懸念のある層はブルーオーシャンである点
いかに優秀なeラーニング教材であってもなかなかログインしてもらえません。良いものを提供すれば広がるかというとそうでもなくて、やはり学校や塾という先生が見守る空間が重要だと考えています。
上記の指摘はまさにeラーニング教材を考える上で、重要なポイントだと思われます。いくら優秀な機能性の高いプロダクトを作ったとしても、学習する習慣や周りの適切なサポートがない限り生徒の学力は伸びないということです。
そういう意味で当社は、きめ細かいサポートをBtoBでできているのでしょう。ここは短期的に構築することはできないノウハウで、強い参入障壁となりそうなポイントです。
株価水準
2019年3月時点
時価総額:約52億円
PER(会社予想 約-倍
まとめ
・画一的な教育制度によって授業についてこれない生徒がいること
・教える人によって教育の質が異なるといった課題
・進学塾ではない、学習の遅れをサポートできる塾の存在が弱いこと
・学習塾、学校の運営サポートするような仕組みの欠如
こういった課題をすららは解決する可能性を秘めていることが今回の調査で理解することができました。
長期投資家としては、やはり社会課題を解決することができるような企業を応援したいものです。
日本の国際競争力の低下は、遡っていけば教育に行き着くと思っています。
画一的な教育によって、学習についていけない生徒は早い段階で自尊心を失ってしまいます。
本来であれば、全ての子供たちが個性があって、違いがあるはずですが、成績という単一の尺度によって図られてしまう現行の教育制度には問題があるでしょう。
その初期の早い段階で、子供に介入してサポートできるような仕組みがあれば、長期で見たときのインパクトは計り知れないとも思います。
当社がやっている事業内容は、そんな社会課題を解決する素敵な事業内容だと感じました。
ゆくゆくは国策としてサポートすべき事業ではないかとも思います。
少し熱がこもってしまいましたが、将来性がある企業として今後も要監視していきたいです。
最後に個別株投資の基礎を学ぶことは、将来の資産形成や財務の知識を高めるために非常に重要です。以下では、お金をかけずに効率的に学ぶことができる3つの簡単な方法をご紹介いたします。
方法①:無料の勉強会・セミナーに参加して体系的に基本を学ぶ
独学で学ぶ際に、無料セミナーに参加することは手軽でおすすめです。
セミナーでは、必要なポイントに絞って学ぶことができ、かつ、一般的な投資参加者の視点を得ることができます。
【無料開催中の勉強会・セミナーの一覧】
◎株式投資の学校
受講生の7割以上がプラスの運用成績を出している、ファイナンシャルアカデミーの人気スクールです。
体験セミナーでは、①お宝銘柄が見つかる3つの基本、②売買タイミングを判断する重要視点、③安定的に利益を出すためのリスク管理法、の3つの視点を学ぶことができます。
8割が損をすると言われる株式投資で、運用実績がマイナスのスクール受講生は、わずか9.4%とHP上では明言しているので、コンテンツにはかなり自信があるのでしょう。
>>【公式】https://www.f-academy.jp/
◎お金の学習・相談サービス『マネイロ』
資産運用やお金の増やし方をプロから動画視聴形式で学べるサービスです。カメラオフ+発言なしで気軽に参加できます。
つみたてNISA、iDeCo、投資信託などの資産運用について、初心者の方にもわかりやすいコンテンツです。
オンラインセミナーは1回30分、スマホでの視聴もOKなので、自宅やカフェからも気軽に参加できるのは嬉しいポイントです。
>>【公式】https://moneiro.jp/
◎投資の達人になる投資講座
投資初心者から経験者まで累計25万人以上が受講したオンライン投資セミナーです。
特徴としては、①講師が営業マンではなく投資の実践者なので、投資のリアルな話が聞ける点、②世界三大投資家ウォーレン・バフェット氏の元義娘、株式投資分析の世界的権威ジェレミー・シーゲル教授など著名な方々から直接情報を得ている点、③他で聞けない投資のノウハウが得られる点、です。
2021年には、最も信頼されるオンライン投資セミナーにも選ばれています。
>>【公式】https://toushi-up.com/
方法②:SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用する
SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用して銘柄を見る習慣をつけることも効果的です。
スクリーニング機能を使うと、さまざまな指標を組み合わせて効率的に銘柄を見つけることができます。
SBI証券では3,600以上の銘柄が取り扱われていますが、スクリーニングを上手に活用することで、素晴らしい銘柄に出会うことができます。
関連記事:小型株・成長株、銘柄一覧まとめ【日本の有望銘柄80社をブログで紹介】
方法③:著名な投資家の本を読む
以下の関連記事で、個人的に読むべき10冊をまとめています。
著名な投資家の本を読むことは、投資における知識と洞察を深めるために重要です。これらの本は、成功した投資家の経験と教訓に基づいて書かれており、貴重な情報を提供してくれます。
投資家の視点や戦略を学ぶことで、市場の動向やリスクの評価についての理解が深まります。
また、投資家の成功や失敗のエピソードを通じて、心構えやリスク管理の重要性も学ぶことができます。これらの本は投資初心者から上級者まで役立つ情報を提供し、自身の投資戦略を構築する上で不可欠な道しるべとなります。

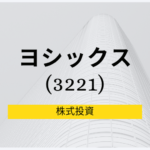

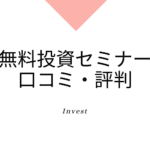



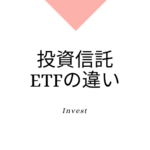

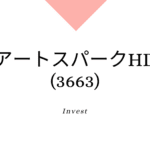



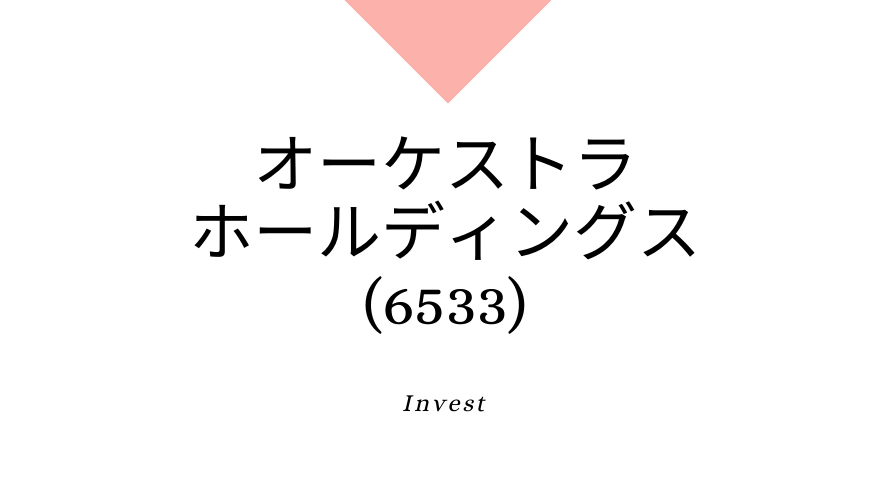
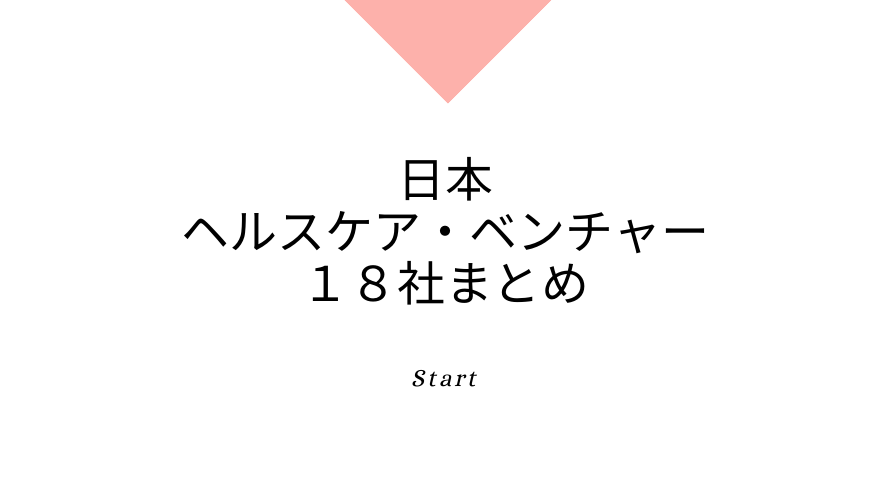
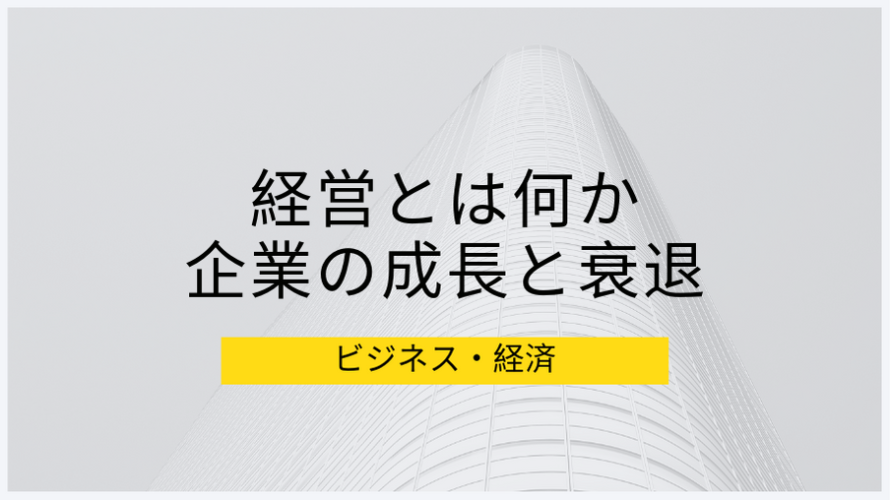


コメントを書く