コプロホールディングス(7059)事業内容、ビジネスモデル、強みと成長可能性
- 2020.09.07
- 株式投資

今回は、コプロホールディングス(7059)の簡易的なリサーチ、分析を実施してみました。
売上高成長率が順調に右肩上がり推移していることと、時価総額が200億円以下だったことがスクリーニングに引っかかったため調査を実施しました。
以下、有価証券報告書2020年度3月期をベースに調査をまとめております。
事業内容
建設技術者派遣事業を単一セグメントとして事業展開をしております。業界としては人材派遣事業に部類されます。
業種別では建築業、土木業、設備、プラント、など派遣業も実施しております。事業の沿革を見てみると、2006年10月に創業し、それ以降日本全国に支店を展開し全国展開を推進しています。
人材の採用に関しては自社運営求人サイト「現キャリ」を運営しています。
ビジネスモデルとしては他の人材派遣事業と一緒であり、就業を希望者を Web 媒体や自社運営メディアから集客、採用し入社後に教育や研修を実施し、顧客企業へ派遣紹介するという事業モデルです。
今後の成長性
建設業界に著しく依存しているため、今後の景気動向や国のインフラ開発需要動向次第で成長が決まってくる領域と言えます。
一方でポジティブな側面では、人材不足が課題となっている領域なので、企業からの人材のニーズというのは底堅いとも言えます。従って当社が優秀な人材や人材をプールできる仕組みを構築できるのであれば成長性はあると考えられます。また当社の時価総額や企業規模はまだまだ、小さいため成長性は十分あり得ると考えられます。
建設業界自体の市場規模は、全体で52兆円(2016年度)ある市場であり、巨大なマーケットであるため、それを考えると需要自体はいきなり無くなることは考えにくいですし、シェアがどこかに独占されるということもなかなか考えにくいでしょう。
参考:https://www.mlit.go.jp/common/001149561.pdf
リスク
今後の成長性のところでも記載した通りですが、人材派遣事業を勝つ建築業界単一セグメントであるための、業界の動向に著しく影響を受ける可能性があります。
また人材採用がキモとなってくるため当社採用力や自社の運営メディアからの集客力に依存するため、例えば競合との競争の激化や Web からの集客依存で、例えば構造変化などが起きた場合は影響を受ける可能性があるのではないでしょうか。
過去業績から経営の健全性
2020年度3月期有価証券報告書を見る限り、2017年から2020年度までは右肩上で売上高成長しており、経常利益も合わせて成長していることが見て取れます。
営業活動のキャッシュフローも2020年度は約11億円のプラスに対して投資キャッシュフローが約1.4億円となっているため、フリーキャッシュフローは十分確保できている模様であります。
自己資本利益率も21.3%と高い水準を維持しており過去の推移を見ても常に20%台を推移してている状態です。
財務状態
20年3月末の貸借対照表を見ると、現金及び預金が約24億円に対して流動負債の合計が約5億円であり有利子負債に関しては見当たらなかったので財務状態はかなり健全な状態であると言えます。
ビジネスモデルの優位性
有価証券報告書からでは、明らかなビジネスモデルの優位性が見当たらなかったが指標を見る限り高い自己資本利益率と利益率の高さから何らかの優位性があるものと考えられるます。
もともと人材派遣事業は利益率の高い業種である一方で、業界動向に影響受けやすい領域であるためなかなか判断が難しいポイントでありますが、当社の特徴としては業界特化型の人材派遣事業法であることを一般的に新規参入の難しい建築業界での長年の実績があることが強みであると考えられます。
実際にどのように人材を確保し、人材教育を実施しているかについては追加の調査が必要です。
経営陣
YouTube に社長のインタビュー動画があったのでそちらが参考になります。こちらの動画を拝見すると社長の考え方というのはどちらかというと人間力をとても重視した経営をされている印象です。
熱い思いを持った社長であることと、自分自身の力でここまでで事業を成長してきたという自信が漲っている印象を受けました。また社内でのアワードなども積極的に実施しているようで社員頑張る仕組みも整っているのではないでしょうか。
社員を顧客と捉えるいう発想はとても面白いと思いました。人材派遣事業においては人材派遣する従業員そのものが重要となってくるため、技術社員の満足度をいかに上げるかということを重視した戦略をとっています。
人材の確保に重点的に取り組んでいる印象と社長のキャラクターやエネルギッシュな印象は実は見えないところで当社の強みとなっているのかもしれません。
株価の水準
2020年9月時点において上場をしてから株価はコロナショック時に一時的に低迷したものの、その後は最高値の3500円をつけて、現在は2000円台後半を推移しています。
指標的には株価は時価総額約150億円であり、PER 約12倍 PBR は約2.5倍であり、人材派遣業界というジャンルの中では PER はそこまで割高の水準ではないかと考えます。
総括
当社の事業モデル自体にはあまり新しさはないものの、業界に特化した人材派遣業業になっているというところと、建設業界自体が人材不足による課題感の高い業界だということが魅力的なポイントであります。
一方で何が強みなのかというところが明確に理解することができなかったため、今後引き続き調査していく必要があります。
一つ仮説として、考えられるポイントとしては会社の人大切にしていくという姿勢そのものが目に見えない形で強みとなっているかもしれません。
特に人材業界においては人材そのものが極めて重要なアセットとなってくるため従業員だけではなく派遣される技術社員の顧客満足度を高めるような施策を愚直に実施しているのであれば、他社との比較において比較優位性を持っている可能性はあり得るでしょう。
※本記事に掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものです。特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また記載事項個人の調査に基づくものであり、100%正確であるとは限りませんので。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
最後に個別株投資の基礎を学ぶことは、将来の資産形成や財務の知識を高めるために非常に重要です。以下では、お金をかけずに効率的に学ぶことができる3つの簡単な方法をご紹介いたします。
方法①:無料の勉強会・セミナーに参加して体系的に基本を学ぶ
独学で学ぶ際に、無料セミナーに参加することは手軽でおすすめです。
セミナーでは、必要なポイントに絞って学ぶことができ、かつ、一般的な投資参加者の視点を得ることができます。
【無料開催中の勉強会・セミナーの一覧】
◎株式投資の学校
受講生の7割以上がプラスの運用成績を出している、ファイナンシャルアカデミーの人気スクールです。
体験セミナーでは、①お宝銘柄が見つかる3つの基本、②売買タイミングを判断する重要視点、③安定的に利益を出すためのリスク管理法、の3つの視点を学ぶことができます。
8割が損をすると言われる株式投資で、運用実績がマイナスのスクール受講生は、わずか9.4%とHP上では明言しているので、コンテンツにはかなり自信があるのでしょう。
>>【公式】https://www.f-academy.jp/
◎お金の学習・相談サービス『マネイロ』
資産運用やお金の増やし方をプロから動画視聴形式で学べるサービスです。カメラオフ+発言なしで気軽に参加できます。
つみたてNISA、iDeCo、投資信託などの資産運用について、初心者の方にもわかりやすいコンテンツです。
オンラインセミナーは1回30分、スマホでの視聴もOKなので、自宅やカフェからも気軽に参加できるのは嬉しいポイントです。
>>【公式】https://moneiro.jp/
◎投資の達人になる投資講座
投資初心者から経験者まで累計25万人以上が受講したオンライン投資セミナーです。
特徴としては、①講師が営業マンではなく投資の実践者なので、投資のリアルな話が聞ける点、②世界三大投資家ウォーレン・バフェット氏の元義娘、株式投資分析の世界的権威ジェレミー・シーゲル教授など著名な方々から直接情報を得ている点、③他で聞けない投資のノウハウが得られる点、です。
2021年には、最も信頼されるオンライン投資セミナーにも選ばれています。
>>【公式】https://toushi-up.com/
方法②:SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用する
SBI証券アプリのスクリーニング機能を活用して銘柄を見る習慣をつけることも効果的です。
スクリーニング機能を使うと、さまざまな指標を組み合わせて効率的に銘柄を見つけることができます。
SBI証券では3,600以上の銘柄が取り扱われていますが、スクリーニングを上手に活用することで、素晴らしい銘柄に出会うことができます。
関連記事:小型株・成長株、銘柄一覧まとめ【日本の有望銘柄80社をブログで紹介】
方法③:著名な投資家の本を読む
以下の関連記事で、個人的に読むべき10冊をまとめています。
著名な投資家の本を読むことは、投資における知識と洞察を深めるために重要です。これらの本は、成功した投資家の経験と教訓に基づいて書かれており、貴重な情報を提供してくれます。
投資家の視点や戦略を学ぶことで、市場の動向やリスクの評価についての理解が深まります。
また、投資家の成功や失敗のエピソードを通じて、心構えやリスク管理の重要性も学ぶことができます。これらの本は投資初心者から上級者まで役立つ情報を提供し、自身の投資戦略を構築する上で不可欠な道しるべとなります。



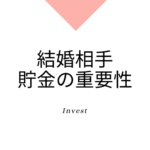
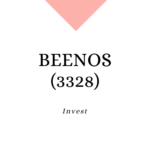


-150x150.png)


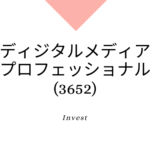


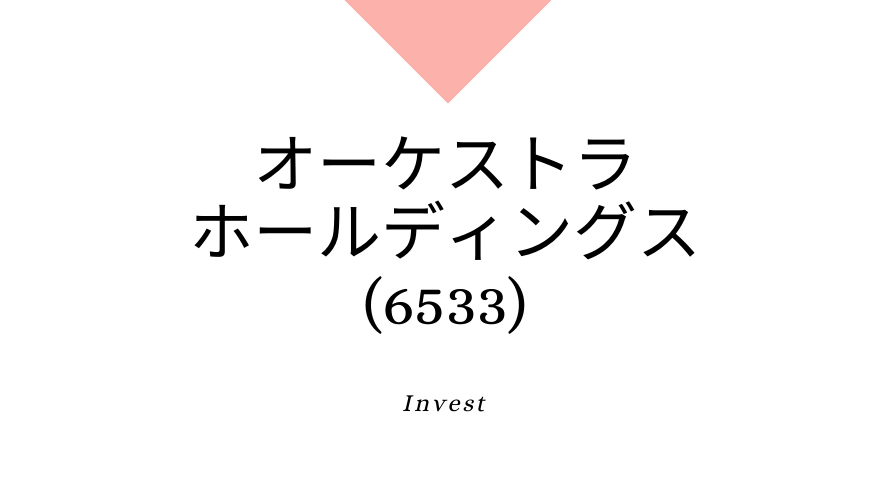
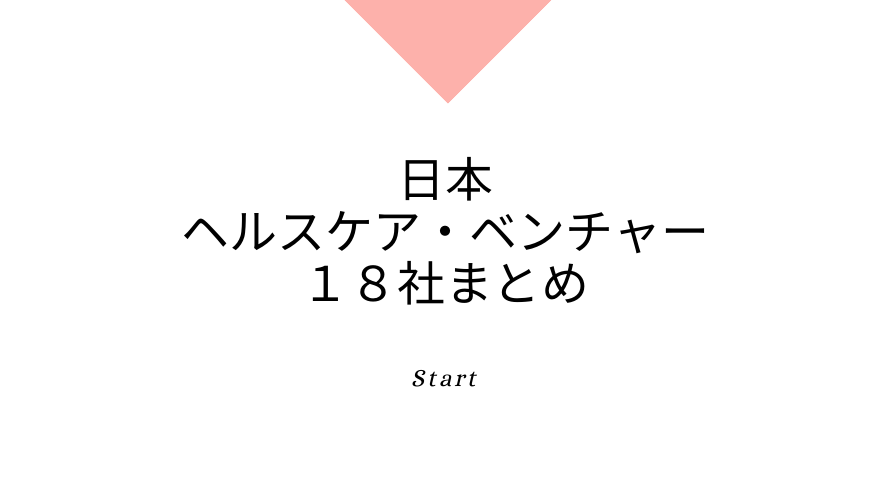
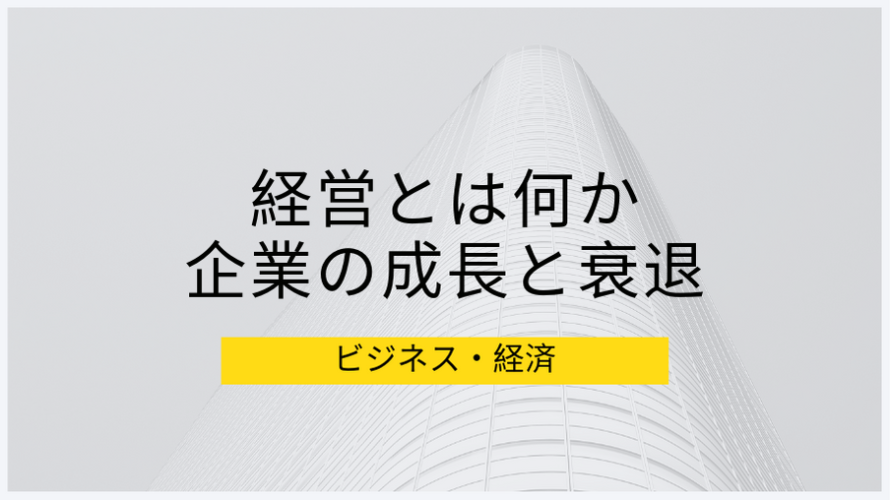


コメントを書く